ゼミ(演習)では、指導教員の専門ごとに分れ、少人数(原則7人以下)で文献を読んだり、グループや個人による研究をしたり、ディスカッションしたりします。
本学科のゼミ(公共社会学研究Ⅰ・Ⅱ)は、社会学だけでなく政治学、経済学、教育学、地理学、情報学など幅広い専門領域で構成されています。
学生は関心のある分野のゼミに入り、地域や国際社会の現象について、課題を設定し、原因を考察・分析する力を学び、4年次には、その成果を卒業論文にまとめます。
 佐野ゼミでは国際社会学など日本と世界を様々な視点から比較し考察するグローバル社会学の視点から研究をしています。3年次は『ファッションで社会学する』という本を用いて演習を行い、誰しもが身近にあるファッションが抱える今日的な課題から世界規模の格差やジェンダー、社会階層についての社会学の視点を理解することができました。演習では章ごとに担当者がレジュメを作り発表し、それをもとに疑問点や深めたい点についてグループ・ディスカッションを行いました。グループ・ディスカッションを通して社会課題に気づく能力や著者の論点を正確に理解する能力を身に付けることができました。また、卒業論文のベースとなる社会学の知識を修得することもできました。
佐野ゼミでは国際社会学など日本と世界を様々な視点から比較し考察するグローバル社会学の視点から研究をしています。3年次は『ファッションで社会学する』という本を用いて演習を行い、誰しもが身近にあるファッションが抱える今日的な課題から世界規模の格差やジェンダー、社会階層についての社会学の視点を理解することができました。演習では章ごとに担当者がレジュメを作り発表し、それをもとに疑問点や深めたい点についてグループ・ディスカッションを行いました。グループ・ディスカッションを通して社会課題に気づく能力や著者の論点を正確に理解する能力を身に付けることができました。また、卒業論文のベースとなる社会学の知識を修得することもできました。
3年生の後期からは、各自が研究課題を設定し、相互に意見を交わしながら研究を進めています。ゼミのグループ・ディスカッションでは、一人では気付けなかった問題や課題について着想を得たり、新たな切り口を見つけたりすることができ、とてもやりがいがあります。また、佐野先生はテーマ選びに悩んでいたら様々なアドバイスや文献の紹介をして下さいます。先生に相談しやすいので研究関心が定まっていない方、新しく研究関心を見つけたい方におすすめのゼミです!
卒業論文指導(佐野ゼミ) M.K
近畿大学附属福岡高等学校出身
 岡本ゼミでは、国際的な視点に立ちながら、政治や文化、民族に関わる社会学を学んでいます。活動内容は学生たち自身が話し合いによって決めるので、型にはまらないバラエティーに富んだゼミです。今年度前期は、韓国威徳大学(慶尚北道慶州市)の李貞煕先生(岡本先生のご友人)の学生たちとZoomによる合同ゼミを行いました。韓国、日本の文化的差異や若者の政治参加について議論をしながら、交流を深めることができました。日本の当たり前が、他国から見れば当たり前ではないということを知り、自身の視野を広げることができたと感じています。また、合同ゼミでは、資料の作成や司会進行も学生たちで行います。そうした意味では、実社会で役立つ実践的な経験を積むことができました。
岡本ゼミでは、国際的な視点に立ちながら、政治や文化、民族に関わる社会学を学んでいます。活動内容は学生たち自身が話し合いによって決めるので、型にはまらないバラエティーに富んだゼミです。今年度前期は、韓国威徳大学(慶尚北道慶州市)の李貞煕先生(岡本先生のご友人)の学生たちとZoomによる合同ゼミを行いました。韓国、日本の文化的差異や若者の政治参加について議論をしながら、交流を深めることができました。日本の当たり前が、他国から見れば当たり前ではないということを知り、自身の視野を広げることができたと感じています。また、合同ゼミでは、資料の作成や司会進行も学生たちで行います。そうした意味では、実社会で役立つ実践的な経験を積むことができました。
岡本先生は、元国連NGO職員で、中国留学やアメリカの大学での客員研究員など海外経験を豊富に積んでこられました。その経験をもとに、幅広い視野、多角的な視点で私たちにアドバイスをしてくださいます。また、岡本先生は学生一人一人に寄り添ってくださる先生です。自分の考えがまとまり切っていなくても、学生の興味関心を真摯に受け止め、適切なサポートをしてくださいます。それに加え、岡本先生は国内外に幅広い人脈を持たれています。今年度の合同ゼミのように、今までにない新しい出会いがあることも、このゼミの魅力だと思っています。
ゼミの雰囲気は穏やかで、自分のペースでじっくりと学ぶことができる環境だと感じています。ゼミ生の関心を持っているテーマは様々で、個性も豊かです。多様なメンバーが集まる岡本ゼミで、自分自身の視野をぐっと広げてみませんか?
公共社会学研究I(岡本ゼミ) M.M
広島県立三次高校出身
 陸ゼミでは、移民問題、都市問題、日中関係などに関する諸問題を研究テーマにし、これらの問題を生み出している社会の現状や仕組みについて深く学びます。3年生の前期は、『移民と日本社会』(永吉希久子著)や『移民をどう考えるか』(カリド・コーザー著)という文献の輪読を行いました。各章をまとめる担当者を中心に全員が自分の意見や感想を発表するため、より内容についての理解が深まって新しい知見を得ることが出来ます。また、陸先生は中国のご出身で海外経験も豊富なので、私たちには無い多角的な視点で物事を捉えており、お話が新鮮でとても勉強になります。
陸ゼミでは、移民問題、都市問題、日中関係などに関する諸問題を研究テーマにし、これらの問題を生み出している社会の現状や仕組みについて深く学びます。3年生の前期は、『移民と日本社会』(永吉希久子著)や『移民をどう考えるか』(カリド・コーザー著)という文献の輪読を行いました。各章をまとめる担当者を中心に全員が自分の意見や感想を発表するため、より内容についての理解が深まって新しい知見を得ることが出来ます。また、陸先生は中国のご出身で海外経験も豊富なので、私たちには無い多角的な視点で物事を捉えており、お話が新鮮でとても勉強になります。 堤ゼミでは社会問題、中でも社会的弱者に関する問題を、教育や労働、社会政策などの観点から、問題をつくり出す社会の仕組みや、その仕組みによって社会の周縁に追いやられている人々の実態について学びます。昨年度の後期はホームレスの人々と出所者を対象に学び、かれらと社会の関係について文献資料や映像資料を用いて議論してきました。
堤ゼミでは社会問題、中でも社会的弱者に関する問題を、教育や労働、社会政策などの観点から、問題をつくり出す社会の仕組みや、その仕組みによって社会の周縁に追いやられている人々の実態について学びます。昨年度の後期はホームレスの人々と出所者を対象に学び、かれらと社会の関係について文献資料や映像資料を用いて議論してきました。 美谷ゼミは、自分たちの関心のあるテキストを選んで輪読し、それについて話し合うという形で進められます。テキストで取り上げられている地域課題や人口問題などについて、内容を確認し、関連する事象を調べた上で、疑問点についてみんなで考え議論します。先生からの助言や解説などもあり、新しい理解を得たり知識を深められるので、毎回ゼミの時間は多くの発見があります。
美谷ゼミは、自分たちの関心のあるテキストを選んで輪読し、それについて話し合うという形で進められます。テキストで取り上げられている地域課題や人口問題などについて、内容を確認し、関連する事象を調べた上で、疑問点についてみんなで考え議論します。先生からの助言や解説などもあり、新しい理解を得たり知識を深められるので、毎回ゼミの時間は多くの発見があります。 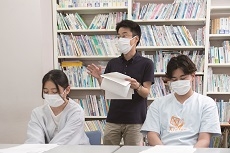 坂無ゼミでは、現在『はじめてのジェンダー論』(加藤秀一著)という本を読んでいます。ジェンダーの知識を一から学ぶことができ、卒業論文や研究に活かすことができます。各章ごとに担当を決め、レジュメ作成、発表を行います。その発表をもとに皆で議論を進めていきます。司会も学生が行い、全員に発表の機会があります。少人数ならではの発言しやすい雰囲気があり、自分のやりたいことを自由にかつ積極的にできる場であると感じています。また、これからは調査や論文の書き方についても学んでいく予定です。
坂無ゼミでは、現在『はじめてのジェンダー論』(加藤秀一著)という本を読んでいます。ジェンダーの知識を一から学ぶことができ、卒業論文や研究に活かすことができます。各章ごとに担当を決め、レジュメ作成、発表を行います。その発表をもとに皆で議論を進めていきます。司会も学生が行い、全員に発表の機会があります。少人数ならではの発言しやすい雰囲気があり、自分のやりたいことを自由にかつ積極的にできる場であると感じています。また、これからは調査や論文の書き方についても学んでいく予定です。
自分が考えていたことに対して、ゼミのメンバーから様々な意見や感想をもらえることはとても貴重な機会となっています。4年生の先輩方と同じ空間で研究や発表を行うこともあります。ゼミでの議論から得られるものはとても大きいものだと実感しています。自分だけでは思いつかなかったアイデア、及ぶことのなかっただろう考え、全てが自分の研究や文献の考察に役立ち、研究や考察の質を高めていくための材料になっています。
 石崎ゼミでは、私たちの興味のある分野について各々で調べ、それをまとめた小レポートを一人ずつ発表してお互いに質問や意見を言い合い、さらに課題を発見した上で次の小レポートの内容を決めるという作業をしています。石崎先生は私たちの意見や質問を聞いた上で新しい疑問や意見、次のテーマについてのアドバイスを与えて私たちを導いてくださいます。
石崎ゼミでは、私たちの興味のある分野について各々で調べ、それをまとめた小レポートを一人ずつ発表してお互いに質問や意見を言い合い、さらに課題を発見した上で次の小レポートの内容を決めるという作業をしています。石崎先生は私たちの意見や質問を聞いた上で新しい疑問や意見、次のテーマについてのアドバイスを与えて私たちを導いてくださいます。
 福本ゼミでは、先生が専門とする地域社会学、環境社会学、農村社会学に関連した文献を読み、担当者がレジュメを作成し、皆で自身の体験などを通した意見交換をしています。レジュメには、要約、意見や考えたことだけでなく、みんなに質問したいことも書くため、意見交換の幅が広がり、楽しく議論できます。また、意見交換をすることで、自分だけでは気づけなかった新たな発見があります。前期は、観光と環境に関する文献を読み、農村地域に目を向けています。私は観光について興味があるため、ゼミでの学習が大変役立っています。後期にはゼミ合宿も予定されており、フィールドワーク、聞き取り調査を行うため、実際に自分たちで調査するという貴重な体験ができます。
福本ゼミでは、先生が専門とする地域社会学、環境社会学、農村社会学に関連した文献を読み、担当者がレジュメを作成し、皆で自身の体験などを通した意見交換をしています。レジュメには、要約、意見や考えたことだけでなく、みんなに質問したいことも書くため、意見交換の幅が広がり、楽しく議論できます。また、意見交換をすることで、自分だけでは気づけなかった新たな発見があります。前期は、観光と環境に関する文献を読み、農村地域に目を向けています。私は観光について興味があるため、ゼミでの学習が大変役立っています。後期にはゼミ合宿も予定されており、フィールドワーク、聞き取り調査を行うため、実際に自分たちで調査するという貴重な体験ができます。 黒川ゼミでは家族社会学を専門とする先生のもとで、ジェンダー、恋愛、結婚、LGBT、子どもの貧困や学習支援などについて考え、議論しています。現在のゼミ生の中でも扱うテーマは多種多様で、それぞれの関心に合ったご指導をしていただいています。
黒川ゼミでは家族社会学を専門とする先生のもとで、ジェンダー、恋愛、結婚、LGBT、子どもの貧困や学習支援などについて考え、議論しています。現在のゼミ生の中でも扱うテーマは多種多様で、それぞれの関心に合ったご指導をしていただいています。
4年生でのゼミでは、それぞれの関心をもとに設定したテーマで卒業論文の内容を詰めていく作業を行います。それぞれの進捗状況を報告するとともに、他のゼミ生や先生から意見や疑問、提案などをもらうことで、論文の内容をより充実したものにしていきます。